先人たちが遺してくれた中に、ことわざや教訓があります。
ことわざ教訓には深い学びが詰まっています。
先人たちが、後世に向けて同じ失敗を繰り返さないように遺してくれた「知恵」です。
僕達は、ことわざや教訓を教育の中で学んでいきます。
それなのに、なぜ人は同じような過ちを何度も繰り返し、傷ついてしまうのか。
又は、人を傷つけてしまうのか。
せっかく先人たちが僕らに失敗させまいと、遺してくれたアドバイスを活かせられないのか?
このテーマについて考えていきたいと思います。
知識はあっても理解がない
「去る者は追わず」
「人の振り見れ我が振り直せ」
「急がば回れ」
日本の義務教育を受けて、これらの言葉を聞いたことがない人は、おそらくいないでしょう。
「知っている」のに、「なぜ行動に活かせない」のでしょうか?
その理由は
人は知識を持っていても、腹落ちしていないと動けないから。
知識は“頭”にあります。
理解は“腹”に落ちて初めて意味を持つということです。
「相手には相手の事情がある」と“頭”ではわかっていても
大切な人が本当に去っていった瞬間、“心”はそうは簡単に納得してくれません。
知識だけでは、感情をコントールできない。
これが人間の特性です。
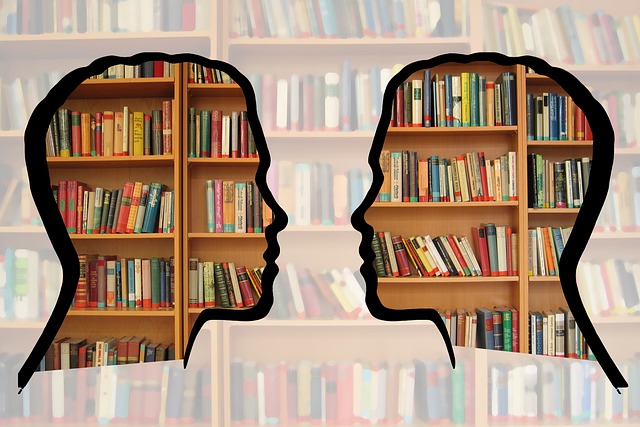
経験しないと痛みがわからない
人は「ああ、そういうことだったのか」と気付くのが遅いものです。
痛みを知らないと、教訓は単なる言葉に過ぎません。
転んで怪我をしてはじめて「気をつけよう」という意味がわかるようになる。
教訓とは、“過去の誰かの失敗”を集約した知恵です。
でも、その失敗を“自分のこと”としてイメージできる人は少ないものです。
“自分は大丈夫”
“自分に限って、そんなことは起きない”
このように思ってしまうのが、人間という生きのもの特性です。
過去にどれだけ忠告があっても、実際に痛い目を見るまでは、深く理解できません。

自分は例外と信じてしまう
心理学には「正常性バイアス」という言葉があります。
簡単に言えば、「自分は大丈夫」と思いたくなる心のクセです。
災害や事故、失敗の前触れがあっても、
「まあ、大丈夫だろう」と油断してしまう感覚です。
この思い込みである「正常性バイアス」が、ことわざや教訓の効力を鈍らせる。
「失敗するって言われてるけど、自分ならうまくやれる」
「他の人はそうだったかもしれないけど、自分の場合は違う」
このように無意識のうちに、信じてしまう。
だから、歴史も繰り返されてしまう。

教訓は“予防”より“傷口”に使う
できることなら先人たちの教訓を自分たちが傷つく前に活かして「予防策」として活かしたいところですが、実際は“起こってしまってからの傷を癒やす薬”として作用しているケースがほとんどです。
失敗した後、悩んだ後、誰かを失った後
起こってから初めて「あのとこわざ、教訓、こういう意味だったのか」「あの人が言っていたことはこのことだったのか」と深く理解できる。
頭で知っていて、更に体験して初めて腹落ちすることができてしまうのでしょう。
教訓は事前に降りかかる問題を完璧に避けて防いでくれるものではないということです。
過ちを犯した後に、傷口を癒やす言葉たちと捉えることもできます。
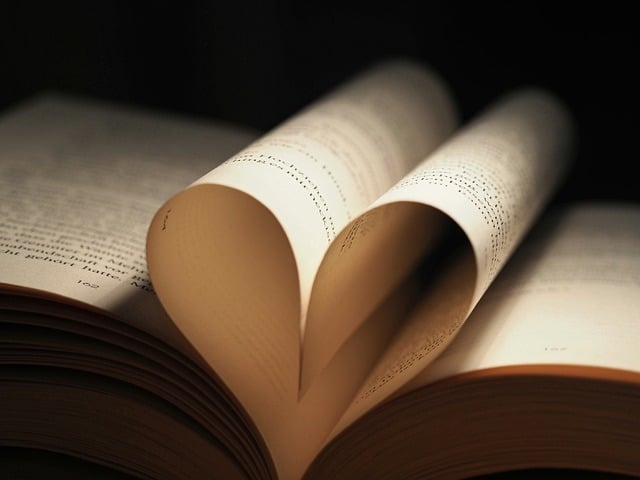
それでも人は、知恵に助けられる
人間は、頭でわかっていても、心がついていなかいもの。
先人たちが遺してくれた教訓や、ことわざを活かせずに失敗するのは自然なことです。
ただ、経験したあとに、
「あのとき聞いた言葉は、こういう意味だったのか」と気付く瞬間が必ずあります。
先人たちの教訓を直接活かせなかったとしても、失敗を通じてそれら教訓の価値に改めて気付き、そこから得られる学びで助けられていきます。
意味がわからないまま聞いていた言葉も、経験を通せば、意味を持ち始めます。
その積み重ねが「考えながら生きる人」と「同じことを繰り返すだけの人」の差になっていきます。

まとめ
人は感情の生き物であるがために同じ過ちを繰り返します。
理屈だけで動けるなら、とっくに人生を変えられているでしょう。
ことわざや教訓は、万能ではありません。
しかし、無意味でもありません。
何か辛い経験をして、自分の頭で考え直す時
先人たちの「言葉」が手がかりになることもあります。
あなたもいずれ、楽しいことばかりではなく、辛いこと、悲しいことに打ちひしがれる時がくるでしょう。
そんなときは、あなたに寄り添う優しい言葉を支えに前に進んでください。
人類が誕生して以来、みんな何かしら自分にとって、辛い経験を通って成長してきたのですから。
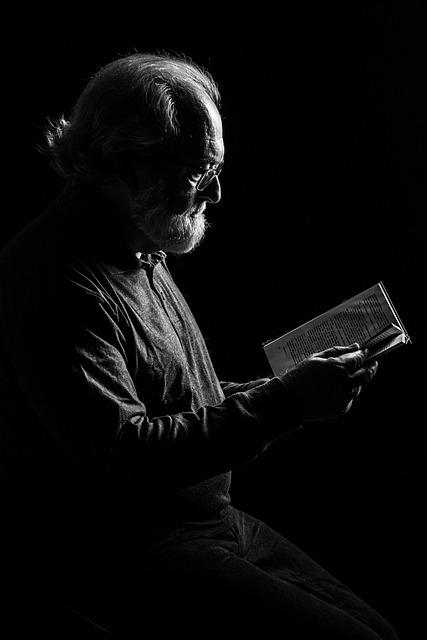
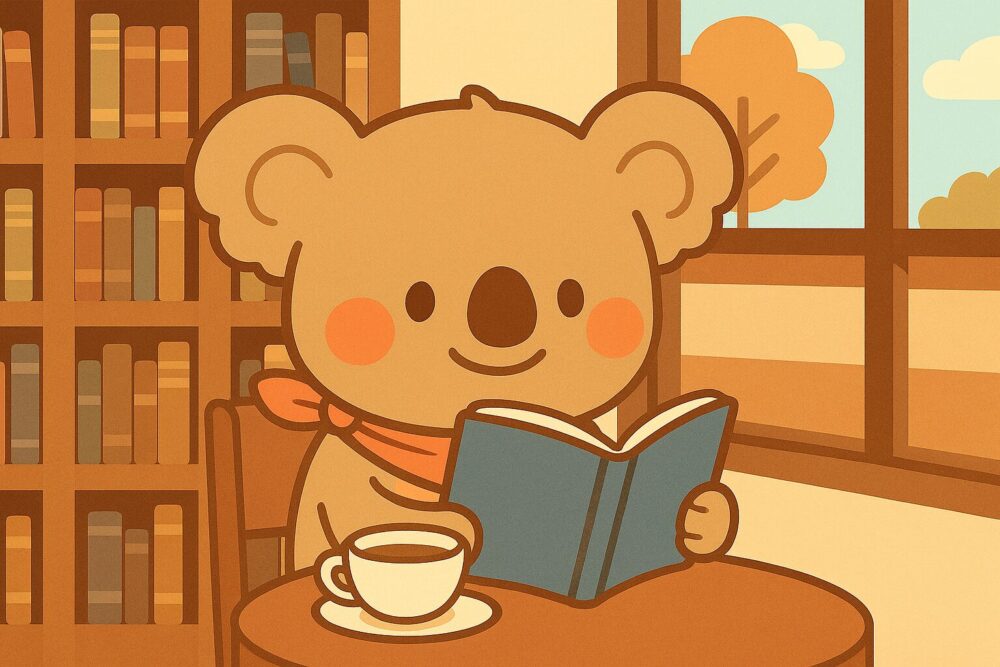


コメント